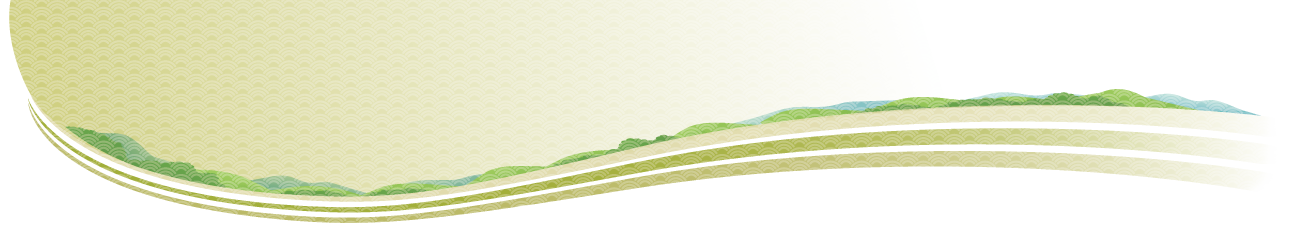
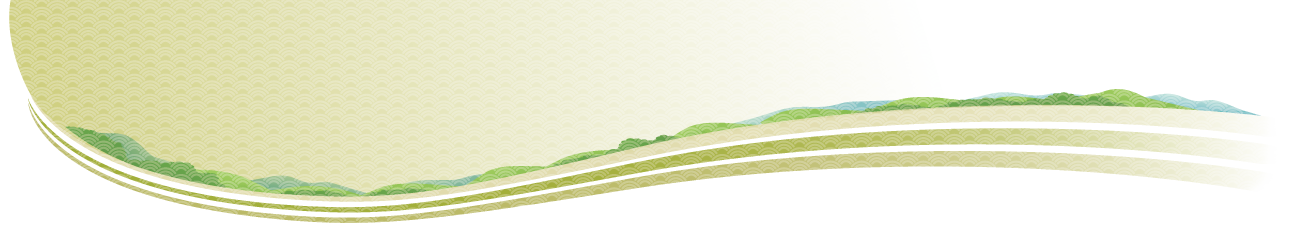
еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгҒҜгҖҒгӮҸгҒҹгҒ—гҒҹгҒЎгҒҢдҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢеёӮз”әжқ‘еҚҳдҪҚгҒ§дәӢжҘӯгӮ’йҒӢе–¶гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
з—…ж°—гӮ„гӮұгӮ¬гҒ«еӮҷгҒҲгҒҰгҖҒгҒҠйҮ‘гӮ’еҮәгҒ—еҗҲгҒ„еҢ»зҷӮиІ»гҒӘгҒ©гӮ’иЈңеҠ©гҒҷгӮӢгҖҢеҠ©гҒ‘еҗҲгҒ„гҒ®еҲ¶еәҰгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ
еӣҪеҶ…гҒ«дҪҸжүҖгҒ®гҒӮгӮӢдәәгҒҜгҖҒдҪ•гӮүгҒӢгҒ®еҒҘеә·дҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҢ»зҷӮдҝқйҷәеҲ¶еәҰгҒ®дёӯгҒ«гҒҜгҖҒиҒ·е ҙгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰеҠ е…ҘгҒҷгӮӢгҖҢеҒҘеә·дҝқйҷәгҖҚгҒЁгҖҒ75жӯід»ҘдёҠгҒ®дәәгҒҢеҠ е…ҘгҒҷгӮӢгҖҢй•·еҜҝеҢ»зҷӮеҲ¶еәҰ(еҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…еҢ»зҷӮеҲ¶еәҰ)гҖҚгҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®дәәгҒҢеҠ е…ҘгҒҷгӮӢгҖҢеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒеұҠеҮәгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘгӮӮгҒ®гӮ’гҒҠжҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰ14ж—Ҙд»ҘеҶ…гҒ«еҪ№е ҙ дҪҸж°‘зЁҺеӢҷиӘІгғ»дҝқеҒҘзҰҸзҘүиӘІгҒ®зӘ“еҸЈгҒ§жүӢз¶ҡгҒҚгӮ’гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
| д»–гҒ®еҒҘеә·дҝқйҷәгӮ’и„ұйҖҖгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚ | еҚ°й‘‘гҖҒйҖҖиҒ·иЁјжҳҺжӣё |
| и»ўе…ҘгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚ | еҚ°й‘‘гҖҒи»ўеҮәиЁјжҳҺжӣё |
| еӯҗгҒ©гӮӮгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгҒЁгҒҚ | еҚ°й‘‘гҖҒеӣҪдҝқгҒ®дҝқйҷәиЁјгҖҒжҜҚеӯҗеҒҘеә·жүӢеёі |
| д»–гҒ®еҒҘеә·дҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚ | еҚ°й‘‘гҖҒеӣҪдҝқгҒ®дҝқйҷәиЁјгғ»еҒҘеә·дҝқйҷәиЁј |
| и»ўеҮәгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚ | еҚ°й‘‘гҖҒеӣҪдҝқгҒ®дҝқйҷәиЁј |
| жӯ»дәЎгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚ | еҚ°й‘‘гҖҒеӣҪдҝқгҒ®дҝқйҷәиЁј |
еҠ е…ҘиҖ…гҒҜгҖҒеҪ№е ҙгҒ®зӘ“еҸЈгҒ«еұҠгҒ‘еҮәгӮ’гҒ—гҒҹж—ҘгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҠ е…ҘиіҮж јгӮ’еҫ—гҒҹж—ҘгҒҫгҒ§гҒ•гҒӢгҒ®гҒјгҒЈгҒҰдҝқйҷәзЁҺгӮ’зҙҚгӮҒгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒдјҡзӨҫгҒӘгҒ©гҒ®еҒҘеә·дҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒҢгӮүеӣҪдҝқгҒ®дҝқйҷәиЁјгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰеҸ—иЁәгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒеӨ§й№ҝжқ‘гҒ®еӣҪдҝқгҒҢиІ жӢ…гҒ—гҒҹеҢ»зҷӮиІ»гӮ’е…ЁйЎҚиҝ”гҒ•гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еұҠгҒ‘еҮәгҒҢйҒ…гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҒ«дҝқйҷәзЁҺгӮ’дәҢйҮҚгҒ«ж”Ҝжү•гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҝ…гҒҡ14ж—Ҙд»ҘеҶ…гҒ«еұҠгҒ‘еҮәгӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгҒ®иў«дҝқйҷәиҖ…гҒҢжӯ»дәЎгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгҒ®и‘¬зҘӯгӮ’иЎҢгҒҶж–№гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰ5дёҮеҶҶгҒҢж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
в—ҶеҮәз”ЈиӮІе…җдёҖжҷӮйҮ‘гҖҖ42дёҮеҶҶ
вҖ» 産科еҢ»зҷӮиЈңе„ҹеҲ¶еәҰгҒ«жңӘеҠ е…ҘгҒ®еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ§еҮәз”ЈгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒҜ40дёҮ4еҚғеҶҶгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е№іжҲҗ21е№ҙ10жңҲгҒӢгӮүгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжқ‘гҒӢгӮүзӣҙжҺҘеҢ»зҷӮж©ҹй–ўзӯүгҒёеҮәз”ЈиӮІе…җдёҖжҷӮйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҢ»зҷӮж©ҹй–ўзӯүгҒёгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гҒҢдёҠиЁҳж”ҜзөҰйЎҚгҒҫгҒ§йҒ”гҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒе·®йЎҚгӮ’дё–еёҜдё»зӯүгҒёж”ҜзөҰгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
вҖ» 1е№ҙд»ҘдёҠз¶ҷз¶ҡгҒ—гҒҰдјҡзӨҫгҒ«еӢӨеӢҷгҒ—гҖҒйҖҖиҒ·еҫҢ6гӮ«жңҲд»ҘеҶ…гҒ«еҮәз”ЈгҒ•гӮҢгҒҹдәәгҒҜгҖҒд»ҘеүҚгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹеҒҘеә·дҝқйҷәгҒӢгӮүеҮәз”ЈиӮІе…җдёҖжҷӮйҮ‘гҒҢж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгҒӢгӮүгҒҜж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҢ»зҷӮиІ»гҒ®гҒҶгҒЎдёӢиЁҳгҒ®иҮӘе·ұиІ жӢ…еүІеҗҲгӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгҒ гҒ‘гҒ§еҢ»зҷӮгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
| зҫ©еӢҷж•ҷиӮІе°ұеӯҰеүҚ | 2еүІ |
| зҫ©еӢҷж•ҷиӮІе°ұеӯҰд»ҘдёҠ70жӯіжңӘжәҖ | 3еүІ |
| 70жӯід»ҘдёҠ75жӯіжңӘжәҖ | 2еүІеҸҲгҒҜ3еүІ(зҸҫеҪ№дёҰгҒҝжүҖеҫ—иҖ…) |
(жіЁ)зҸҫеҪ№дёҰгҒҝжүҖеҫ—иҖ…гҒЁгҒҜгҖҒеҗҢдёҖдё–еёҜгҒ®еӣҪдҝқеҠ е…ҘиҖ…гҒ§гҖҒ70жӯігҒӢгӮү74жӯігҒ®дҪҸж°‘зЁҺиӘІзЁҺжүҖеҫ—145дёҮеҶҶд»ҘдёҠгҒ®иҖ…гӮ’гҒ•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҗҢгҒҳжңҲеҶ…гҒ®еҢ»зҷӮиІ»гҒ®иҮӘе·ұиІ жӢ…йЎҚгҒҢйҷҗеәҰйЎҚгӮ’и¶…гҒҲгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒз”іи«ӢгҒҷгӮӢгҒЁй«ҳйЎҚзҷӮйӨҠиІ»гҒЁгҒ—гҒҰгҒӮгҒЁгҒӢгӮүж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
иЁҲз®—ж–№жі•гҒҜдёӢиЁҳгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠе№ҙйҪўгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
| еҢәеҲҶ | йҷҗеәҰйЎҚ | еҢ»зҷӮиІ»гҒҢдёӢиЁҳгҒ®е ҙеҗҲгҒ®йҷҗеәҰйЎҚ | |
| дҪҸж°‘зЁҺиӘІзЁҺдё–еёҜ | жүҖеҫ—901дёҮеҶҶи¶… | 252,600еҶҶ | еҢ»зҷӮиІ»гҒҢ842,000еҶҶгӮ’и¶…гҒҲгҒҹе ҙеҗҲ 252,600еҶҶ+(еҢ»зҷӮиІ»з·ҸйЎҚ-842,000еҶҶ)Г—1пј… |
| жүҖеҫ—901дёҮеҶҶд»ҘдёӢ | 167,400еҶҶ | еҢ»зҷӮиІ»гҒҢ558,000еҶҶгӮ’и¶…гҒҲгҒҹе ҙеҗҲ 167,400еҶҶ+(еҢ»зҷӮиІ»з·ҸйЎҚ-558,000еҶҶ)Г—1пј… |
|
| жүҖеҫ—600дёҮеҶҶд»ҘдёӢ | 80,100еҶҶ | еҢ»зҷӮиІ»гҒҢ267,000еҶҶгӮ’и¶…гҒҲгҒҹе ҙеҗҲ 80,100еҶҶ+(еҢ»зҷӮиІ»з·ҸйЎҚ-267,000еҶҶ)Г—1пј… |
|
| жүҖеҫ—210дёҮеҶҶд»ҘдёӢ | 57,600еҶҶ | ||
| дҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺдё–еёҜ(жіЁ1) | 35,400еҶҶ | ||
(жіЁ1)дё–еёҜдё»гҒЁеӣҪдҝқеҠ е…ҘиҖ…гҒҢдҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺгҒ§гҒӮгӮӢдё–еёҜ
| еҢәеҲҶ | йҷҗеәҰйЎҚ | еҢ»зҷӮиІ»гҒҢдёӢиЁҳгҒ®е ҙеҗҲгҒ®йҷҗеәҰйЎҚ | |
| зҸҫеҪ№дёҰгҒҝжүҖеҫ—иҖ… | иӘІзЁҺжүҖеҫ— В 690дёҮеҶҶд»ҘдёҠ |
252,600еҶҶ | еҢ»зҷӮиІ»гҒҢ842,000еҶҶгӮ’и¶…гҒҲгҒҹе ҙеҗҲ 252,600еҶҶ+(еҢ»зҷӮиІ»з·ҸйЎҚ-842,000еҶҶ)Г—1пј… |
| иӘІзЁҺжүҖеҫ— В 380дёҮеҶҶд»ҘдёҠ |
167,400еҶҶ | еҢ»зҷӮиІ»гҒҢ558,000еҶҶгӮ’и¶…гҒҲгҒҹе ҙеҗҲ 167,400еҶҶ+(еҢ»зҷӮиІ»з·ҸйЎҚ-558,000еҶҶ)Г—1пј… |
|
| иӘІзЁҺжүҖеҫ— В 145дёҮеҶҶд»ҘдёҠ |
80,100еҶҶ | еҢ»зҷӮиІ»гҒҢ267,000еҶҶгӮ’и¶…гҒҲгҒҹе ҙеҗҲ 80,100еҶҶпјӢ(еҢ»зҷӮиІ»з·ҸйЎҚ-267,000еҶҶ)Г—1пј… |
|
| еҢәеҲҶ | еӨ–жқҘ(еҖӢдәәеҚҳдҪҚ)гҒ®йҷҗеәҰйЎҚ | е…ҘйҷўпјӢеӨ–жқҘ(дё–еёҜеҚҳдҪҚ)гҒ®йҷҗеәҰйЎҚ | |
| дёҖиҲ¬ | 18,000еҶҶ | 57,600еҶҶ | |
| дҪҺжүҖеҫ—иҖ…2(жіЁ1) | 8,000еҶҶ | 24,600еҶҶ | |
| дҪҺжүҖеҫ—иҖ…1(жіЁ2) | 8,000еҶҶ | 15,000еҶҶ | |
(жіЁ1)дё–еёҜдё»гҒЁеӣҪдҝқеҠ е…ҘиҖ…гҒҢдҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺгҒ§гҒӮгӮӢдё–еёҜ
(жіЁ2)дё–еёҜдё»гҒЁеӣҪдҝқеҠ е…ҘиҖ…гҒҢдҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺгҒ§гҖҒеҗ„жүҖеҫ—гҒӢгӮүеҝ…иҰҒзөҢиІ»гғ»жҺ§йҷӨгӮ’е·®гҒ—еј•гҒ„гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«0еҶҶгҒ§гҒӮгӮӢдё–еёҜ
дё–еёҜеҶ…гҒ§еҗҢдёҖгҒ®еҢ»зҷӮдҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒжҜҺе№ҙ8жңҲ1ж—ҘпҪһзҝҢе№ҙ7жңҲ31ж—ҘгҒ®12гӮ«жңҲй–“гҒ«гҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгҖҢеҢ»зҷӮдҝқйҷәгҖҚгҒЁгҖҢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҖҚгҒ®дёЎж–№гҒ«иҮӘе·ұиІ жӢ…гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®иҮӘе·ұиІ жӢ…гҒ®еҗҲиЁҲгҒҢдёӢиЁҳгҒ®йҷҗеәҰйЎҚгӮ’и¶…гҒҲгҒҹе ҙеҗҲгҖҒз”іи«ӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒи¶…гҒҲгҒҹйҮ‘йЎҚгҒҢж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гӮӮгҖҒеҢ»зҷӮиІ»гҒҜй«ҳйЎҚзҷӮйӨҠиІ»гҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒҜй«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢжңҲеҚҳдҪҚгҒ§йҷҗеәҰйЎҚгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰиҮӘе·ұиІ жӢ…гӮ’и»ҪгҒҸгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҖҺй«ҳйЎҚеҢ»зҷӮгғ»й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·еҗҲз®—зҷӮйӨҠиІ»еҲ¶еәҰгҖҸгҒ§гҒҜгҖҒгҒ•гӮүгҒ«ж®ӢгҒЈгҒҹиҮӘе·ұиІ жӢ…йЎҚгӮ’е№ҙеҚҳдҪҚгҒ§еҗҲз®—гҒ—гҖҒж”ҜзөҰгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮ
| жүҖеҫ—еҢәеҲҶ | йҷҗеәҰйЎҚ | |
| дҪҸж°‘зЁҺиӘІзЁҺдё–еёҜ | жүҖеҫ—901дёҮеҶҶи¶… | 212дёҮеҶҶ |
| жүҖеҫ—901дёҮеҶҶд»ҘдёӢ | 141дёҮеҶҶ | |
| жүҖеҫ—600дёҮеҶҶд»ҘдёӢ | 67дёҮеҶҶ | |
| жүҖеҫ—210дёҮеҶҶд»ҘдёӢ | 60дёҮеҶҶ | |
| дҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺдё–еёҜ | 34дёҮеҶҶ | |
| жүҖеҫ—еҢәеҲҶ | йҷҗеәҰйЎҚ | |
| зҸҫеҪ№дёҰгҒҝжүҖеҫ—иҖ… | гҖҖиӘІзЁҺжүҖеҫ— гҖҖ 690дёҮеҶҶд»ҘдёҠ |
212дёҮеҶҶ |
| гҖҖиӘІзЁҺжүҖеҫ— В гҖҖ380дёҮеҶҶд»ҘдёҠ |
141дёҮеҶҶ | |
| гҖҖиӘІзЁҺжүҖеҫ— В гҖҖ145дёҮеҶҶд»ҘдёҠ |
67дёҮеҶҶ | |
| дёҖиҲ¬ | 56дёҮеҶҶ | |
| дҪҺжүҖеҫ—иҖ…2(жіЁ1) | 31дёҮеҶҶ | |
| дҪҺжүҖеҫ—иҖ…1(жіЁ2) | 19дёҮеҶҶ | |
(жіЁ1)дё–еёҜдё»гҒЁеӣҪдҝқеҠ е…ҘиҖ…гҒҢдҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺгҒ§гҒӮгӮӢдё–еёҜ
(жіЁ2)дё–еёҜдё»гҒЁеӣҪдҝқеҠ е…ҘиҖ…гҒҢдҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺгҒ§гҖҒеҗ„жүҖеҫ—гҒӢгӮүеҝ…иҰҒзөҢиІ»гғ»жҺ§йҷӨгӮ’е·®гҒ—еј•гҒ„гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«0еҶҶгҒ§гҒӮгӮӢдё–еёҜ
ж¬ЎгҒ®е ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“е…ЁйЎҚиҮӘе·ұиІ жӢ…гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеӣҪдҝқгҒ®зӘ“еҸЈгҒёз”іи«ӢгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒеҫҢгҒӢгӮүдҝқйҷәеҜҫиұЎеҢ»зҷӮиІ»гҒҢж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
пјңгҒҠжҢҒгҒЎгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгӮӮгҒ®пјһ
пјңгҒҠжҢҒгҒЎгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгӮӮгҒ®пјһ
пјңгҒҠжҢҒгҒЎгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгӮӮгҒ®пјһ
пјңгҒҠжҢҒгҒЎгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгӮӮгҒ®пјһ
пјңгҒҠжҢҒгҒЎгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгӮӮгҒ®пјһ
жө·еӨ–зҷӮйӨҠиІ»гҒ®ж”ҜзөҰеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬еӣҪеҶ…гҒ§дҝқйҷәзөҰд»ҳгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҢ»зҷӮиЎҢзӮәгҒ«йҷҗгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжІ»зҷӮзӣ®зҡ„гҒ§жёЎиҲӘгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜж”ҜзөҰеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ®гҒ§гҒ”жіЁж„ҸгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
пјңгҒҠжҢҒгҒЎгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгӮӮгҒ®пјһ
зҷӮйӨҠиІ»з”іи«ӢжӣёгҖҖгҖҖгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒҜгҒ“гҒЎгӮү
гҖҖвҖ»з”іи«ӢгҒҢжң¬дәәд»ҘеӨ–гҒ®е ҙеҗҲгҒҜ委任зҠ¶гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷ
гҖҖвҖ»з”іи«ӢгҒҢжң¬дәәгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҚ°й‘‘гҒҜдёҚиҰҒгҒ§гҒҷ
委任зҠ¶гҖҖгҖҖгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒҜгҒ“гҒЎгӮү